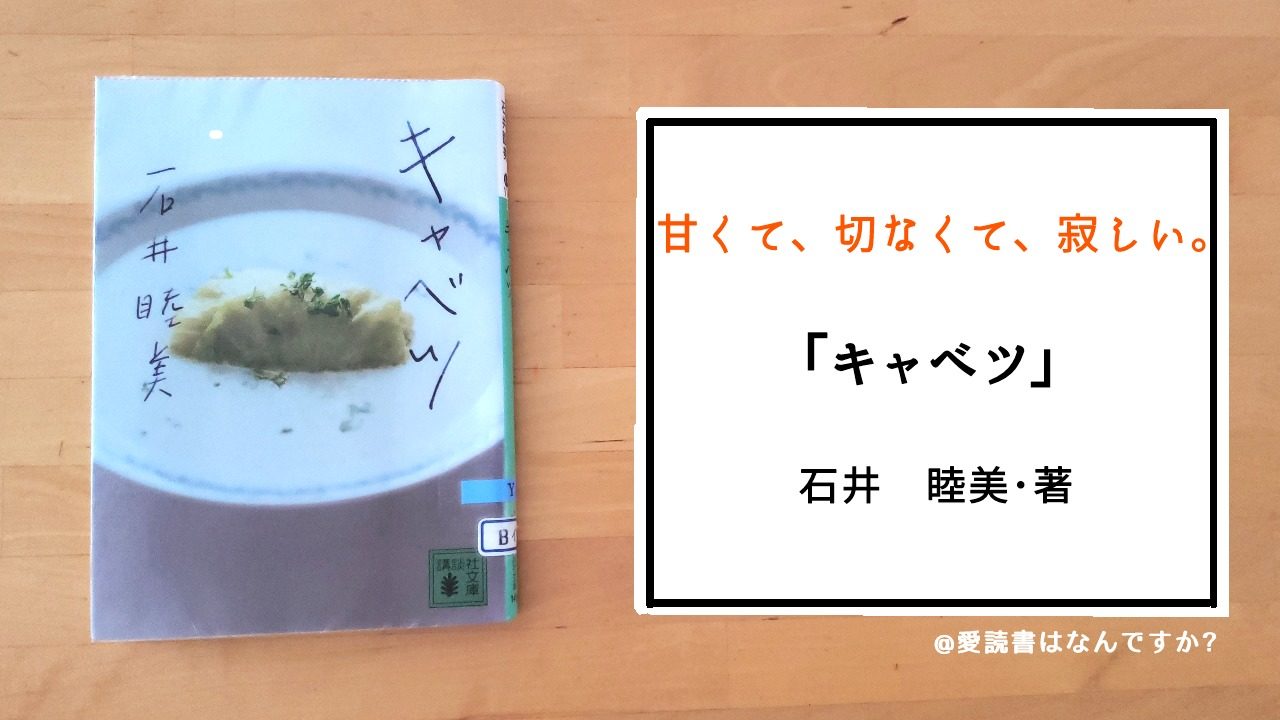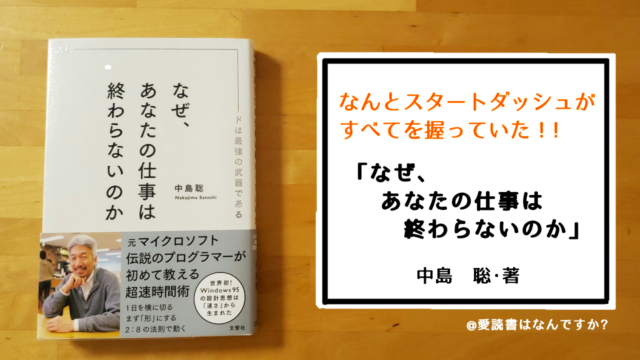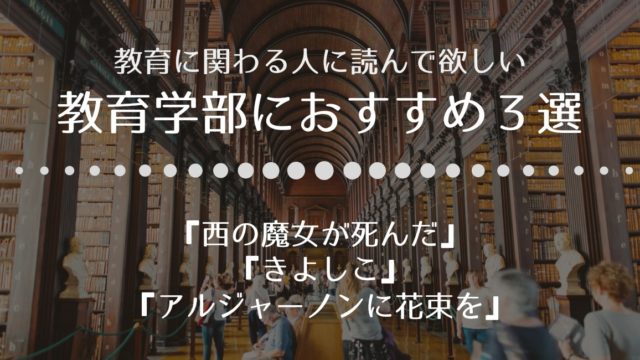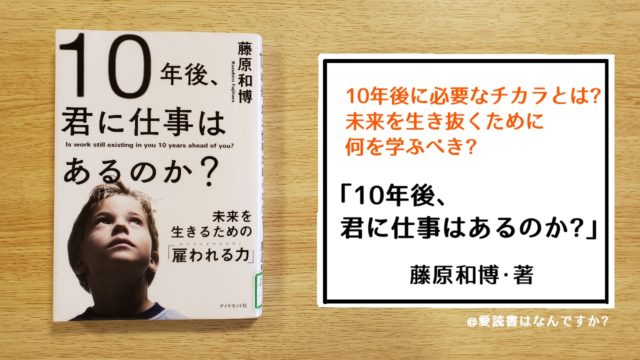何気ない日常を切り取ったショートフィルムのような物語、とでも表現したらいいのでしょうか。
10代の繊細な心が、日常のきらめきと共に、ただただ眩しい。
自我と客観を往来する心の会話に深く共感する自分がいて、私もまだ大丈夫と安心する気持ちになります。
何に安心するかって?
それはもちろん自分にもまだピュアな部分が残っていることに対して、です。
食べ物の話が好きで、題名に見つけると引き寄せられるところがあります。
10代向けの本を探してこの題名を発見し、裏表紙の紹介文を読んだ時にはもうメロメロになっていました。
中二の時に父親が亡くなり会社勤めを始めた母親に代わってご飯を作るようになった主人公の「ぼく」が、最初に思い浮かべたのはキャベツだった。
ぼくはご飯を炊き、みそ汁とサラダを作り、買ってきた鳥のから揚げをチンし、それから毎日の家事の合間に勉強して大学生になる。
雨が降りそうになったら映画を止めて家に帰り、洗濯物を取り込む。
小腹がすいたらキャベツをちぎって、キャベツのうまたれをかけて食べる。
そんな日常のなかで、日々それなりに努力を重ねていけばどんなことでもある程度はできるようになるんだ、という確信に満ちた哲学を築いた青年は、何気ない日常に起こる、何気ない出来事から自身の心の成長を築いてゆく。
-紹介文より-
この物語は「ぼく」の14歳から19歳までの6年間の話なのですが、彼の心の奥底にしまわれた感情が、あるきっかけで浮上する瞬間が一番のハイライトです。
ふとした言葉で思いがけない自分の感情に気づき、驚き、心底戸惑う。
そんな瞬間に共感できる人はどれくらいいるのでしょうか。
本当はこんな風に思っていたんだ、と、自分のために泣いたことのある人は。
自分だけの特別な体験のように思えますが、意外に多いのかもしれません。
あまりに私的で語られることのない話は、常にひっそりと心の奥へしまわれますから。

ちなみに冒頭で「ショートフィルムのような」と書きましたが、この話は主人公の5年間分だけがスパンと切り取られた物語です。
人生の起承転結なんて、それは終わってからの後付けであって、生きる毎日はただただ続いていきます。
だから結論も決着も、ハッピーエンドもバッドエンドも、未来に伸びる瞬間に決めつけることは出来ません。
どうしても物語に意味を求めてしまうのは、人間の習性なのか、習慣なのか。
そんな事を思いながら、表紙を眺めると。
うん、いい写真。食べ物の話が好きだと、また思います。
10代の皆さんならこの先「ぼく」と彼女はどうなるんだろう、と思いを馳せたりするのでしょうが、上の年代の私は肩をバンと叩いて「ま、うまくやんなさいよ!」という気持ちで本を閉じます。
そしてまた、「せいぜい頑張んなさいよ!」というエールを送る気持ちで、この本を10代の皆さんに勧めたいと思っています。
ちょっと肩の力を抜いて、優しい気持ちになりたい時におススメの本です。