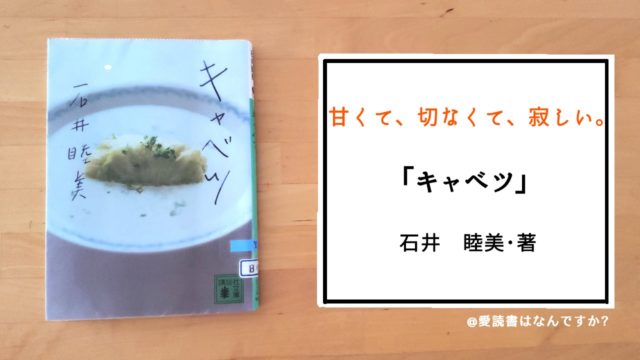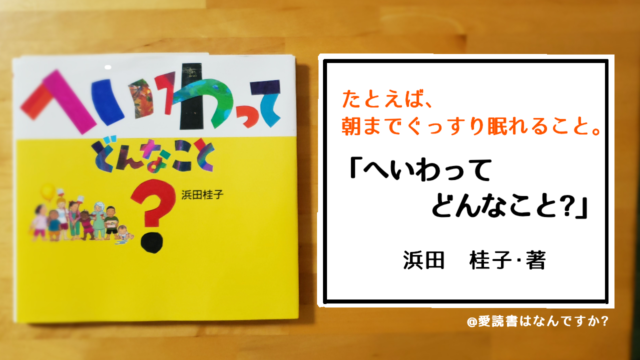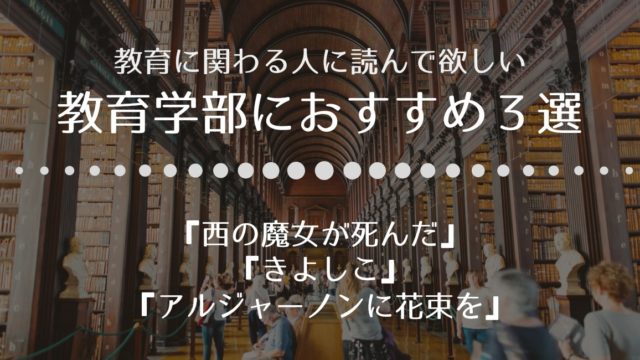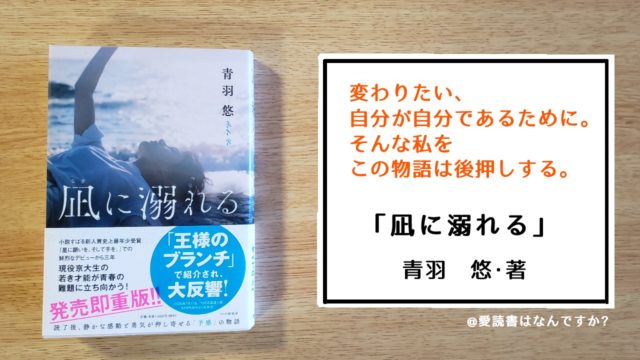人が人を生むことは善なのか

女性、特に30代から40代の女性に反響の大きい作品だと言います。それはこの『夏物語』に、女性なら誰もが必ず通る「踏み絵」があるからではないでしょうか。
ここでいう踏み絵とは「結婚」「出産」という社会の慣習ともいうべき道のことです。
現代のようにライフスタイルや人生設計が変わり結婚適齢期がなくなっても、女性の体の「妊娠適齢期」や「分娩適齢期」は変わりません。平均寿命が延びたとしても、女性の生殖年齢は大昔から限りがあるのです。
この作品は生殖倫理というテーマに踏み込んで、生まれること、産むこと産まないこと、生きることを考える長編です。
いわゆる「人生の夏」の季節の終わりには、人は必ずなんらかの答えを出さなければなりません。たとえ答えを出せないとしても時は非情に過ぎ、「結婚」「出産」の問いにはYESかNOのチェックがつけられます。すべては結果論の世界なのですが。
この作品は2008年に芥川賞を受けた短編『乳と卵 (文春文庫)』で描いた女性たちの続きとして、8年後に38歳となった主人公・夏子のその後の物語です。
『乳と卵』では少女が女性として成熟した身体に代わることへの戸惑いと嫌悪が描かれ、この『夏物語』では生殖期間と倫理感の狭間で自分の答えを出すために苦悩する心の内が描かれます。
「生む生まない」だけの問題ではなく、そこには性の葛藤、家庭の貧困、身近な人の死など幅広い要素が複雑に絡みこんでいます。
なかでも今回比重を置かれているのは、メインテーマともいえる「生植倫理としての人工授精」の観点です。
人工授精から生まれた人物が印象的に描かれていますが、そのセリフの重みもまた真実と感じます。
「人が生まれること」に正面から向き合う

作者である川上未映子さんは自身は現在43歳。ご自身も8年前に結婚、小学1年生になる長男がいます。
朝日新聞のインタビューでは「子どもを産んだ今でも、女性にとって産まない方が自然なのではという気持ちがある。出産は利己的なもの。産んだ側の人間として、自分は何をしたのかを手放さずに考え続けたい(2019.8.4掲載)」とあります。
実生活で結婚し出産した作者が、自分の経験をどのように作品に融和したのか注目されるところでしょう。
川上さん独特の文章が淡々と密度濃く続き、主人公の想いが暴走するように見えて全方位からの意見が描かれているところが意外にフェアだと感じます。
シングル、シングルマザー、子持ちの主婦など登場する女性たちの生々しさ、度々議論される家族観や倫理観は読者の固定概念を簡単に覆すのではないでしょうか。
あまりに時代めいた女性像や倒錯した親子関係に疑問が浮かぶ点もありますが、改めて考えれば、大なり小なり家族単位のつながりはそんなものかもしれないとも思えてきます。
あなたの正解はでましたか?

生まれることに自己決定はない。だが産むことには自己決定がある。この目も眩むような非対称を、どうやって埋めればよいのか? 母になる女たちは、この暗渠をどうやって越したのか? どうすれば、そんな無謀で勝手な選択ができるのか? 作者は、「産むこと」の自己決定とは何か? という、怖ろしい問い、だが、これまでほとんどの産んだ者たちがスルーしてきた問いに、正面から立ち向かう。
――上野千鶴子(「文藝」秋季号)
物語には何らかの終着点が無ければ結末となりませんが、たとえ主人公がどの道を選んだとしても、私たち読者は納得できないのではないかと思います。
生殖倫理という分野には、まさに答えは無いのでしょう。線引きさえも出来ない分野であり、そこには一人ひとりの倫理観念があるだけです。
その倫理観は母になった者には生まなかった女性の、母とならなかった者には生んだ女性の互いの心の内に消えない火種を残していくような気がします。正直この問題はどちらの道を選んだとしても、もう一方への思いは残るのではないでしょうか。
しかし、私たちは「考え続けること出来る」ことを忘れてはいけないと思うのです。
対極の前で考え続けることにきっと大きな意味があるのだと、私は信じていたいのです。