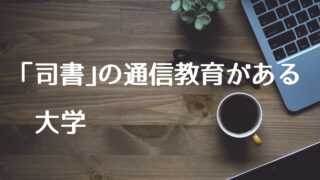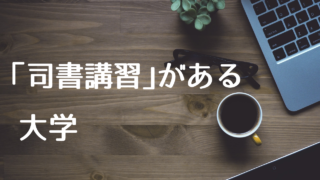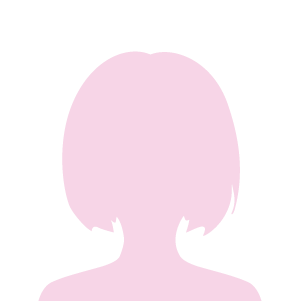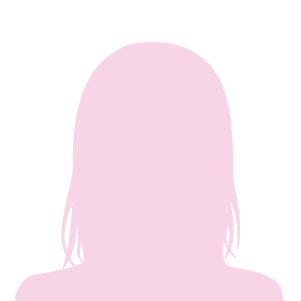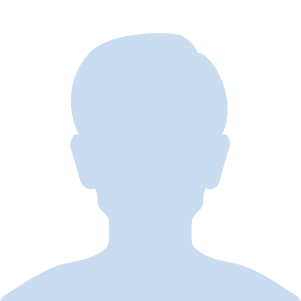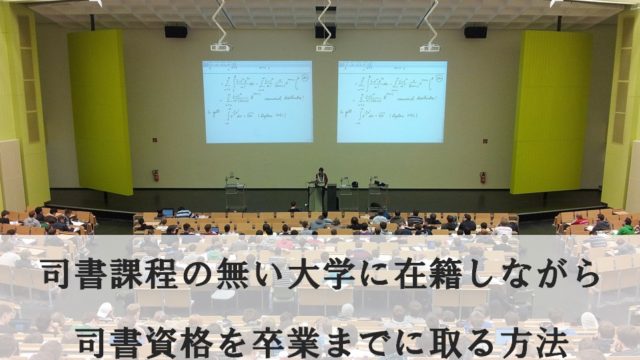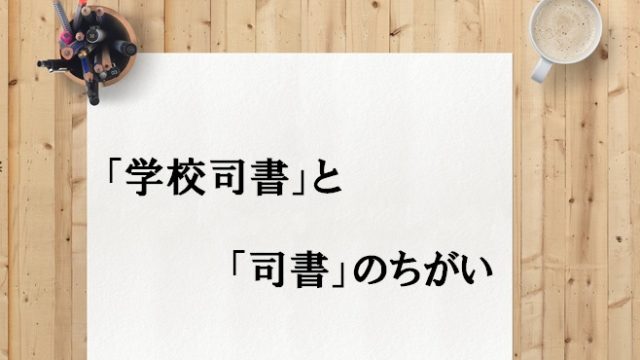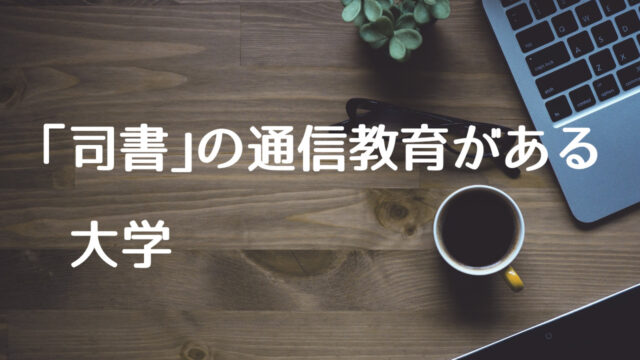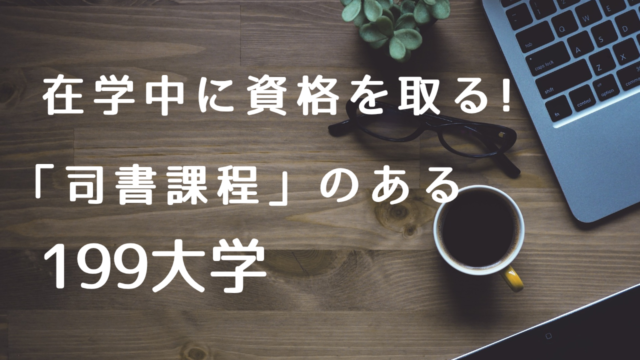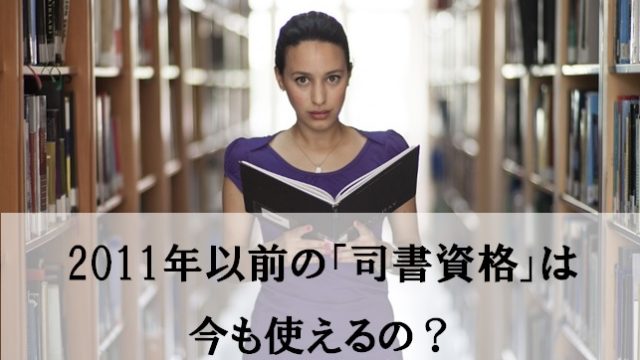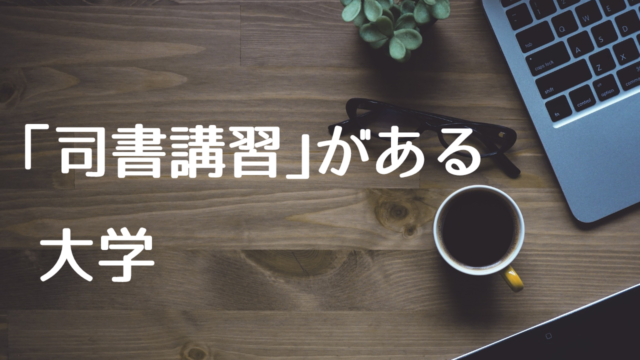司書になりたい!と思っても、意外にわかりにくいものです。
就職するにはどこから手を付ければよいの?
業界内には、情報がバンバン飛び交っているのです。
司書職を希望している学生さんや二度目の求職中の方、どうぞご活用下さい!
司書の採用情報は意外にわかりにくい

小さい時から読書好きだった私は、「図書室の先生」に憧れていました。
ですから司書職の詳細はよくわからないながらも、とりあえず教員免許と共に司書の資格の取得を視野に入れて大学を選びました。
大学4年になって実際の就職を考えたときに、司書の求人情報は本当に漠然としていました。
司書の授業はあるのに、教授に聞いてもキャリアサポート室に行っても詳細がわからなかったのです。
よくある職業ガイド本等には、抽象的なことしか書いてありませんでした。
そして公共図書館職員は地方公務員採用試験の受験が必須だとわかった頃には、時はすでに遅かった…という苦い経験をしました。
そんな経緯のあった私ですが、その15年後に縁あって司書になった今、ようやく司書業界の就活全貌が見えてきました。
司書の採用について
まずは図書館を大きく4つに分類して考えてみます。
1.公共図書館(国、県、市)
2.学校図書館(公立、私立)
3.大学図書館(国公立、私立)
4.その他の図書館
1.公共図書館
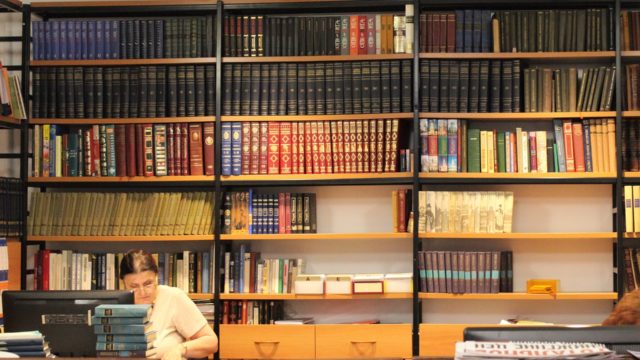
公共図書館に正規職員として勤務するためには、自治体(国・都道府県・市)の公務員試験を受けて合格する必要があります。
国立国会図書館の職員採用試験
国の公共図書館は国立国会図書館永田町本館・関西館・国際こども図書館があります。
*この3館の採用には国家公務員の受験が必要ですが、これは国家公務員試験とは別に独自に実施する国家公務員採用試験です。
*司書の資格は必要なく、また大卒程度の試験ですが大学卒業資格も必要ありません。
*総合職と一般職で別個に募集枠があります。
*詳細は国立国会図書館のHPで見ることが出来ます。
3月中旬に募集が出ます。
県(都・道・府)立図書館職員採用試験
県職員採用試験を受けます。
*各県の県立図書館のHPで確認できますが「司書職」で募集を行っているかどうかは自治体によって異なります。
県職員として採用された後の配属先の一つとして配置されるという形が一般的なようですが、司書専任で採用する県もあるようです。
(例えば2019年採用試験では神奈川県が大卒司書の募集をしています。)
地方公務員試験は大体5月頃から募集が始まり、6月下旬頃から一次試験が始まります。3月に募集要項で調べることが出来ます。
市(区)立図書館職員採用試験
市(区)の市職員採用試験を受けます。
*県と同様に自治体によって採用形態が異なります。
実習教諭という名称で採用するところもあります。
また新設図書館の予定がある年には専任司書を募集することもあります。
要項をみてもわからない時は、自治体に確認してみましょう。
地方公務員試験は大体5月頃から募集が始まり、6月下旬頃から一次試験が始まります。3月に募集要項で調べることが出来ます。
2.学校図書館
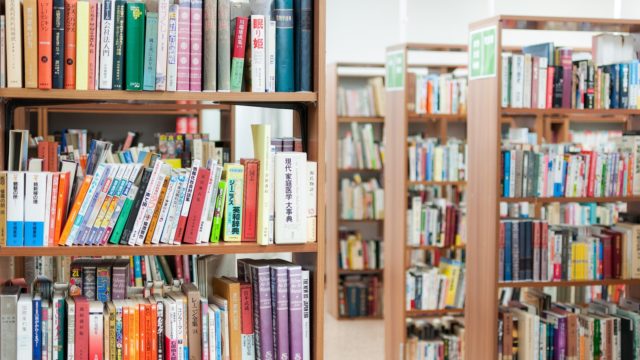
○公立の小・中・高の学校司書
- 自治体の公務員試験を受けることが多いようです。
- 一例…県立高校学校司書は県職員(大卒の行政職)、市立高校は市職員(高卒・短大卒の学校事務職)。公共図書館同様、採用後に職員として配属されています。一度司書として配属されたら、学校図書館と県立図書館の中でずっと配属されるということでした。
- 一例…小中学校は臨時職員や公務補助といった名称で募集されている非常勤職員が多い。いわゆる非正規雇用なので、時間給であったり契約期間も期限があります。募集期間もまちまちですが、おおむね学期の始まる1か月前が多いという情報がありました。ハローワークで求人募集を見ることができます。
- 国立大付属小中学校の学校司書は大学職員になります。私が募集要項を見た時には教員免許と司書免許の両方が必要でした。大学職員採用試験を受験します。
○私立の小・中・高の学校司書
- 採用が必要になった場合に求人を出します。
- ハローワーク等で一般募集しますが、「紹介」も多い印象です。
学内に守るべき個人情報(住所から成績まで)が多いので、身元の知れた「信頼」出来る人物が欲しいからだと思います。 - 教職員として正規雇用の学校もあれば非常勤雇用だったり学校の方針によって違いますが、私立は学校図書館が充実しているところが多く、概ね熱心な学校が多いです。
○学校図書館には「学校司書」を置くことが、学校努力として定められています(出典;学校図書館法)ので、募集の人員が比較的高いジャンルかもしれません。
3.大学図書館

○大学図書館の司書
- 正規職員としての採用は一般の就職活動と同じです。新卒者募集があるかを確認しましょう。
- 公立私立問わず採用が必要になった場合に求人を出します。
- 大学職員としての正規雇用か契約雇用かは大学によって異なります。
4.その他の図書館(専門図書館)

企業運営の図書館は、採用が必要になった場合に求人を出します。ほとんど定期採用はされていないようです。
専門的な図書を扱う企業の中に設置されていたり、私設美術館や私設博物館に併設された図書館などが、これにあたるでしょう。特定の専門知識を求められることもあります。
例)公益財団法人 味の素 食の専門図書館「食の文化ライブラリー」
㈱味の素が食文化の研究支援・普及の為にオープンさせた、食に特化した企業運営の図書館です。開館時間内であれば誰でも無料で利用することが出来、閲覧のほかに貸し出しも行っている。研究目的だけでなく、毎日の献立作りや日常の話題つくりのために広く一般にも門戸を開放しています。
タイプ別おすすめ図書館司書
ここまで読んでお分かり頂けたと思いますが、司書と一口に言っても様々なジャンルがあります。まずは自分がどの分野の図書館に勤務したいかを選ぶことが第一の入り口になります。
低年齢の子どもとの読書活動に関わりたいのであれば、国際こども図書館、公共図書館の幼児と児童向けの部屋や、小学校の学校司書などがおすすめです。
読み聞かせ等を中心とした触れ合いが得意な人が求められます。
当然小さい子どもと話したり、またその親たちと話す機会も多くなるので、児童心理や幼児教育などの知識が必要です。
YA(ヤングアダルト)とよばれる中高生の読書活動に関わるには、中高の学校司書、公共図書館のYA担当などが適しているでしょう。
この世代の読書は教育活動とも関連してきます。
最近はアクティブラーニングとよばれる「生徒参加型の自主的な学びの場」として、学校図書館を活用しようという動きも出てきました。
生徒が調べたい主題に対してのアプローチを現場で補佐する役目として学校司書の存在は欠かせません。
司書として教育に関心を持ち、知識を得ることが大切です。
「アクティブラーニング」
生徒が能動的に学ぶことによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る内容の教育のこと (2012年8月中央教育審議会答申より)
より専門的な分野に特化した担当の司書となれば、国立国会図書館や大学図書館、企業図書館の勤務になります。
学生や教員、もしくは企業内での研究テーマに沿った資料を収集するなどの業務が多くなります。
自分がどの分野の司書になりたいかを見極めよう
自分の得意なことや関心があること、あるいは苦手なことも考慮してみるといいですね。
小さい子どもが苦手な人には低年齢対象の司書は難しいでしょうし、教育の現場で働きたいと思っている人には中高の学校司書の職場などが特にやりがいが感じられると思います。
司書になりたいからと言って手当たり次第に受けるのではなく、自分の特性を生かして的を絞り、採用に必要な情報の収集と勉強をすることが肝心です。
見極めた志望動機のもとにアンテナを高く張って、遅れの無い活動が出来るようにしましょう!
また、司書の資格が問われない採用もありますが、仕事をするからには知識が無ければ表面的な対応しか出来ません。2ヶ月間の受講で取れる、通学型の「司書講座」や、自宅のインターネットを利用しての通信講座もあるので、資格をお持ちでない方には是非おススメします。