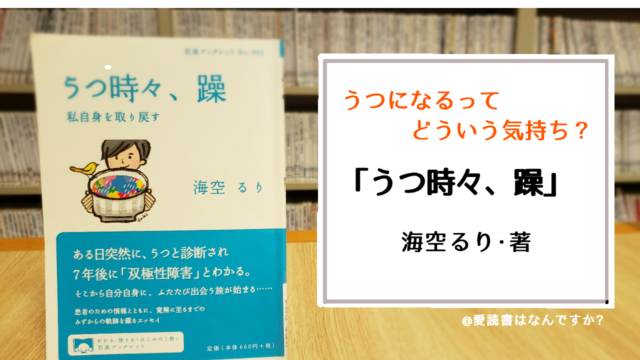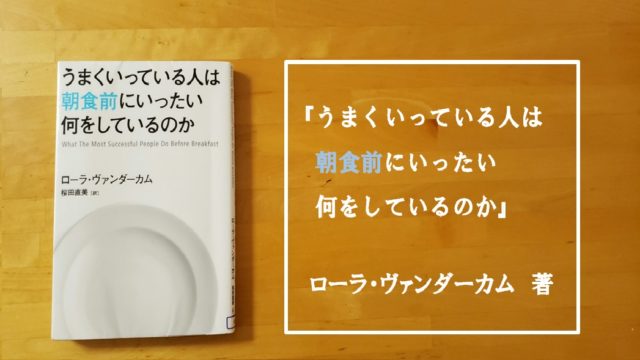「バカすぎる」と思うこと、とは。

多用される「バカすぎて」というフレーズ。
今風に言えば、マウンティング女子の脳内ダダ洩れ、となるのでしょうか。
「バカすぎて」という言葉には、
相手への怒りと、相手を少し見下して自分とは違うジャンルの人間だという突き放しの気持ちがあるように思います。
辞めたい辞めたいと辞表を握りしめている主人公からすれば「こんな悲惨な仕事現場はマウンティングでもしなければ、やってられない!」という心情なのでしょう。
つまりそれはどういうことになるのかと考えると…
相手を見下す心の裏には自分の弱さがあるということ。
自分を棚に上げるというよりは、相手との間に線を引いて必死に自分のプライドを守っている姿が、なんとも切なく感じられて。
彼女が必死に守っているプライドとは、彼女の弱さとは。
作家・早見和真さんが狙ったところ

もともとの版元である角川春樹事務所の角川社長からのオファーは、
「前作の『イノセント・デイズ』っぽくて『小説王』っぽいもの(ミステリーっぽくて、熱い友情を感じるもの)」だったそう。
しかし、早見和真さんは前からやりたいと思っていたコメディを書こうと決心。
題名がまず浮かび、書店を舞台にしようと思い立ちます。
「書店が舞台なら、まず書店員さんも、書店に来る人も興味を持ってくれるだろうと。
身近だから書きやすかったというわけではないんです。
むしろ書きにくい場所でした」
(引用;小説丸)
本屋は本当に必要なのか、ということを、かなり考えて挑んだと言います。
「本屋のある街とない街、どちらに暮らしたいかと言われたら、僕は本屋のある街に暮らしたい。豊かさという意味で。
その気持ちに忠実に書けば、必然的にエールになるだろうと思いました。
ことさらそれを書くわけじゃなくて、その気持ちを常に胸においておくイメージで書きました」
(引用;小説丸)
敢えて書店を中心に置くことで、書店の実情を盛り込みたい。
そこに生まれる人間模様や、出版社や書店の販売や人事の制度を描くことで業界全体へエールを送りたい…そんな思いが『店長がバカすぎて』を作ったような印象をうけました。
これは書店へのラブレター

個人的には主人公・谷原京子の中の、もっと濃ゆい心の内を深く知りたかった!と思います。
しかしここは「書店」にスポットをあてての物語なわけで。
そう考えつつ探って読むと相応に、”書店と出版社の関係”や、”本の帯がどのようにして作られているのか”など書店の裏側探検的な面白さがあります。
なんといっても描かれる書店員たちの本への偏愛は、まさに作者からの「書店へのラブレター」です。
だいぶ「本屋大賞」狙っているところがプンプンの本書ですが、実際の書店員さんは「うん、リアル!」と思うのか、「こんなキレイ事じゃない!」と思うのか、聞いてみたいですね。
でも題名はかなり上手!!
題名だけで読んでみようと思いますもの。お見事です!