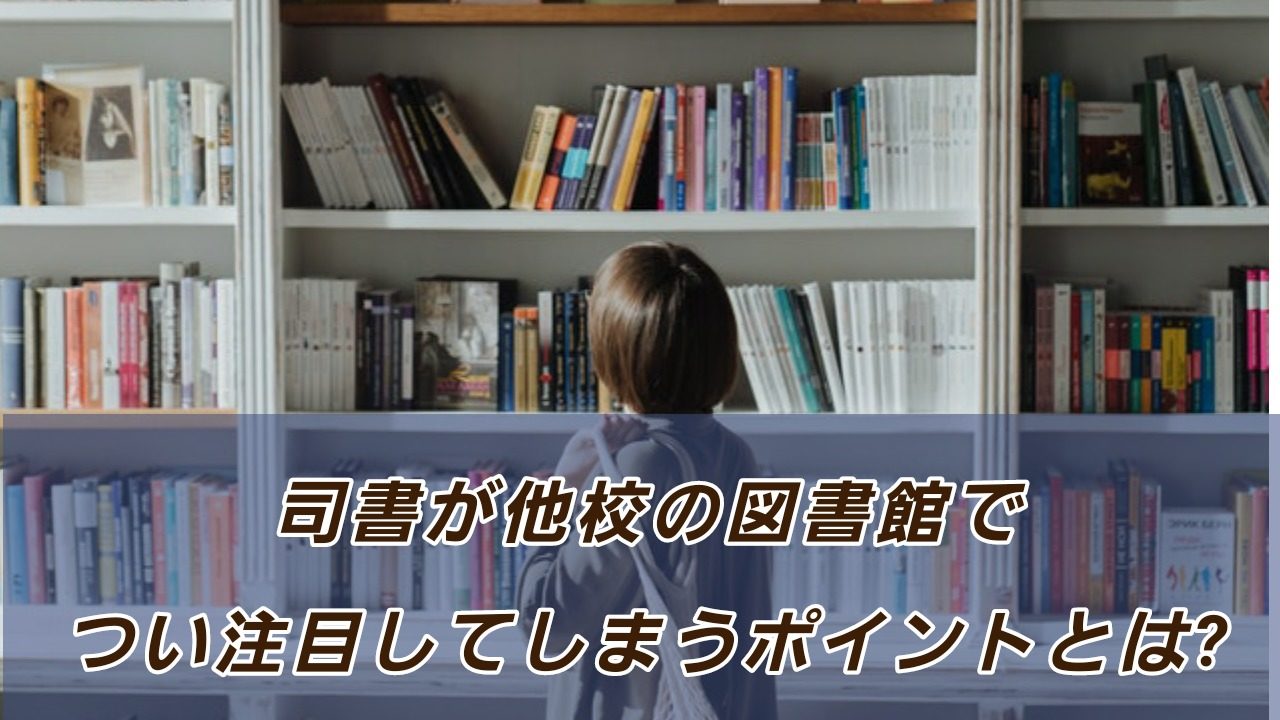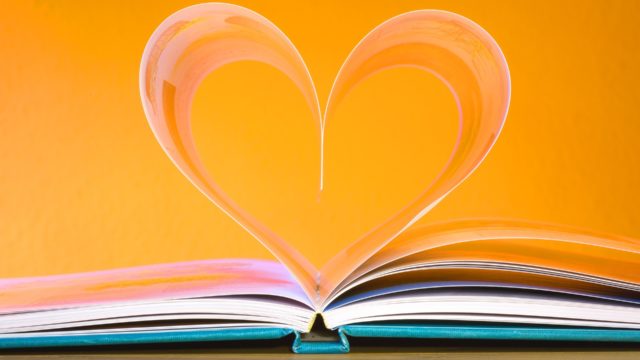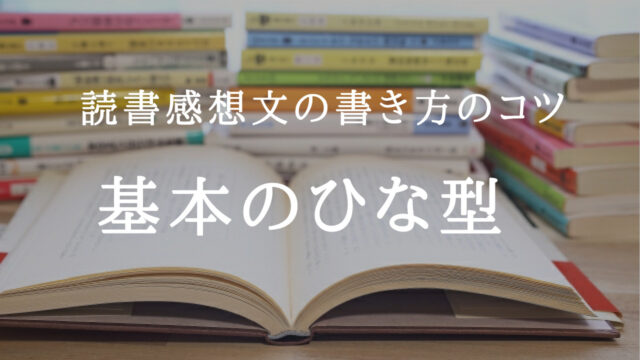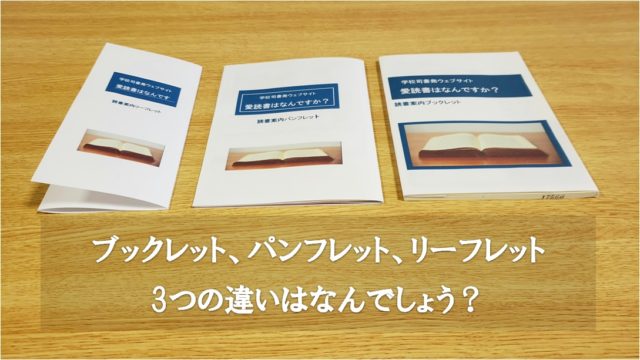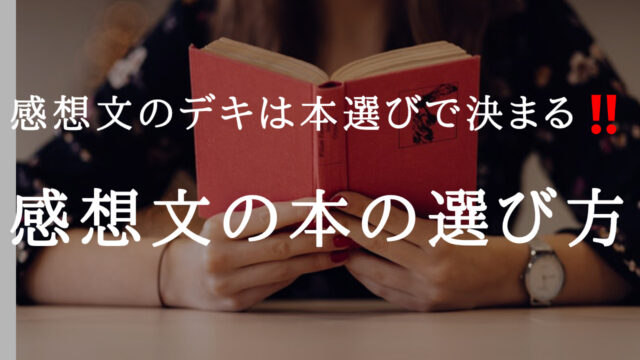学校司書をしていると、どうしても他校の図書館が気になってしまいます。
研修での学校訪問や、我が子の授業参観の時にも、何か学べることはないかとついつい足を運んでしまう「学校図書館」。
今回はそんな学校司書が注目してしまう、独断的な「学校図書館・個性の見極めポイント」をお話しします。
これを読んだら、図書館の見方が変わってしまうかもしれませんよ^^
学校図書館の個性の見つけ方!
他校の図書館が気になる!
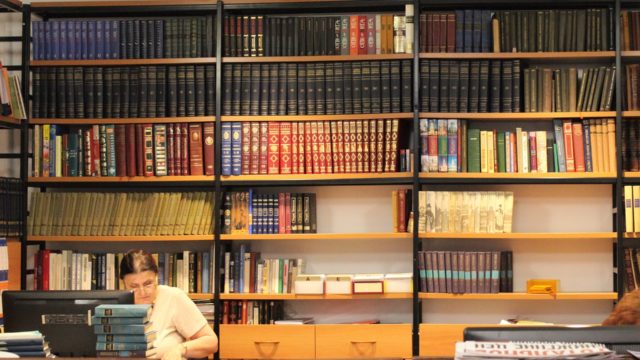 公立出身の私が私学教育に初めて接したとき、かなりのカルチャーショックを受けました(笑)
公立出身の私が私学教育に初めて接したとき、かなりのカルチャーショックを受けました(笑)
一言で言えば、「自由度の高さ、選択肢の広さ」でしょうか。
当然ですが公立校で重要視されることに「公平性」「公共性」があります。これはリベラルな視線、偏らない視点です。
ところが私学教育で筆頭に来るのは「建学の精神」です。すべてが建学の精神に基づいて教育理念があり、教育方針があります。
元々私塾から始まったり宗教が起点となることが多い私学では、”建学者の信奉する書物”が学問の礎だったりします。
ですから、学校の「知識の源」となる書庫、つまり図書館は、そうりゃあもう学校のカラー満載なんです!
公立学校では絶対出来ないような選択もやり方も、ここでは方針に合えばオールオッケー^^その奥深さにクラクラしました。
私は私学の図書館司書を複数校で経験しているのですが、学校によって配置や選書基準も全然違います。
どの方法もそれぞれに理由があり、納得の工夫があり、興味は尽きません。
そんなわけで、つい図書館ウォッチャーの血が騒いでしまう私の注目ポイント5つご紹介します。
入ってすぐ、雑誌の種類を見る

定期購読の雑誌名ほど、購読者層があらわに出るものはないんじゃないでしょうか?
雑誌はターゲットが明確なので、一瞥でその学校の雰囲気がわかってしまうトコロがあります。
特にニッチな専門誌を見つけたときなどは、嬉しくてついニヤリとしてしまいます。
時事問題などを扱う雑誌でも「ニューズウィーク日本版」と「NEWSがわかる」の両方が置いてあったりすると理解度に応じて選ぶことが出来て親切だなと思います。
「月刊バレーボール」や「月刊ベースボールクリニック」などメジャーな雑誌以外にも水球、卓球、ソフトボールなどがズラリと並んでいるスポーツ強豪校は、まさに圧巻。
「月刊秘伝」という武術系の雑誌を見つけたときは感嘆の声が出てしまいました。私が見たときの特集は“精神力を鍛える”。さすがです、これを読み込んでいる選手にはかなわない気がします。
「月刊MOE」という絵本系のほのぼの雑誌から「文藝春秋」「文藝」「新潮」などまである学校には、文学の本気を感じます。個人的には「すばる」と「小説すばる」の両方あると嬉しくなりますね。
「non-no」「メンズnon-no」などファッション誌がある学校も意外に多く、図書館もカジュアルになってきているのだなあとしみじみ。
「クロワッサン」や「レタスクラブ」など家事系雑誌が多かった図書館ではつい理由を質問してしまったのですが、親元を離れて暮らす寮生などに人気があるそうです。なるほど。
学校独自の○○文庫を捜す

歴史の長い名門校では、卒業生や土地ゆかりの著名人による寄贈本が「○○文庫」などの名称で別置されている場合があります。
その方の執筆された本だけでなく、参考資料としての貴重本や、珍しい初版本なども多く見ごたえのあるコレクションです。
貴重な展示物というだけでなく、その方との学校の関わりを知ることもまた、学校の個性を理解する手助けになります。
分類500~700台の本棚
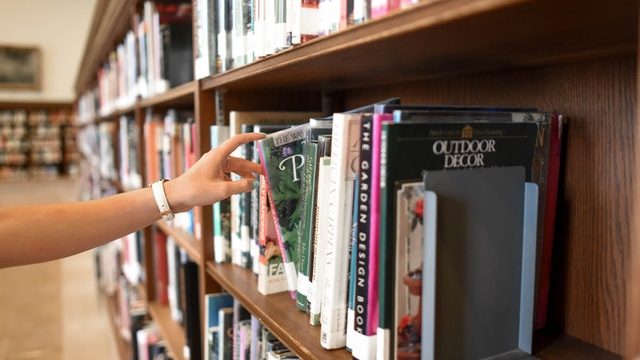
NDCの500~700台は「技術・工学」「産業」「芸術・美術」なのですが、個人的には選書にクセがある分野だと思っています。
例えば、一般的な家政系の本や、食に関する本、スポーツの精神論から競技の技術論、美術書から音楽に関する本など、中高生の理解度に照らし合わせつつも網羅したいという悩み多き箇所なのです。
運動部、文化部両方ともの部活動に関する本もここに入ります。美術書や書道などに関するものは値の張る本も多いので、参考にさせてもらうことも多々あります。
学校の専門分野に興味しんしん

高専、そう理系分野に特化した5年制の国立高等専門学校の図書館にお邪魔したときは、本当に楽しかった!
訪れたのは主に情報・電子系の学科があるキャンパスだったのですが、専攻学科の「AI」関連図書の棚は、言葉がグラデーションのように連なる題名の背表紙で埋め尽くされている!
十進法0番台を占める棚の割合の多いことと言ったら。司書ならではのマニアックな目線ですが、こんなに総記の棚が続くのーーー!?って、ワクワクしながら回遊しました。
授業でレポート作成も多いと聞きましたが、レポート作成に関する本も初歩的なものから高度なものまで多彩です。
確かに15歳から21歳までが集まる高専ですので豊富なバリエーションが必要なのかもしれませんが、これだけあれば必要な人に行き渡るよね、ともはや親心でウルウルきました。
そして意外だったのは、913の小説の棚も充実していたことですね。自宅外生も多い高専生、気分転換に一人時間に読書をする学生も多いそうです。新刊本も充実していました。
専門性のある学校の本並びには、ワクワクが詰まっています!
新着図書の選び方で傾向を知る

新刊本の発売日は全国どこでももちろん同じ。店頭になくても予約で入手できますので、選択の機会は日本中どこの学校図書館も同じです。
しかし悲しいかな、国会図書館ではありませんのですべての図書を入れるわけにはいかないのです。
そこで学校ごとの「基準」と「予算」に従って本の選定が始まるわけですが…
ですから学校によって、新刊本を広いジャンルでまんべんなく拾っていくことろもあれば、偏った分野や作家をガッツリ入れるところもあり、私などはむしろ「入っていない話題の本」の方が気になってしかたありません。
また「新書」も図書館ではお馴染みのジャンルの一つですが、どこの出版社の新書を揃えているかも気になります。岩波、ちくま、中公あたりはスタンダードな気がしますが、SBクリエイティブ新書が並んでいると「攻めますなあ!」という感じがします。
ブックレットも同様で、岩浪ブックレットに並んでブルーバックスがあると安心感がありますので、ついチェックしてしまいます。
おたく職業病スレスレの新刊チェック、意外と楽しめます。
まとめ

実はそれぞれに個性がある学校図書館ですが、なかなか比べて見るという経験はない分野です。
中の人だからこそわかる「比べるポイント」を挙げてみましたが、いかがだったでしょうか。
その他にも、本棚の配置が十進法通りではない、くつろぎスペースがソファや畳などで充実している(中には冬場コタツが登場する学校もあります)などもわかりやすい注目箇所です。
オリジナリティは濃すぎるのも面白いし、全く無くても使いやすい。個性が無いのが個性だ、という理論はかなり正論ですよね。是非参考になさってみて下さい^^